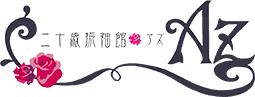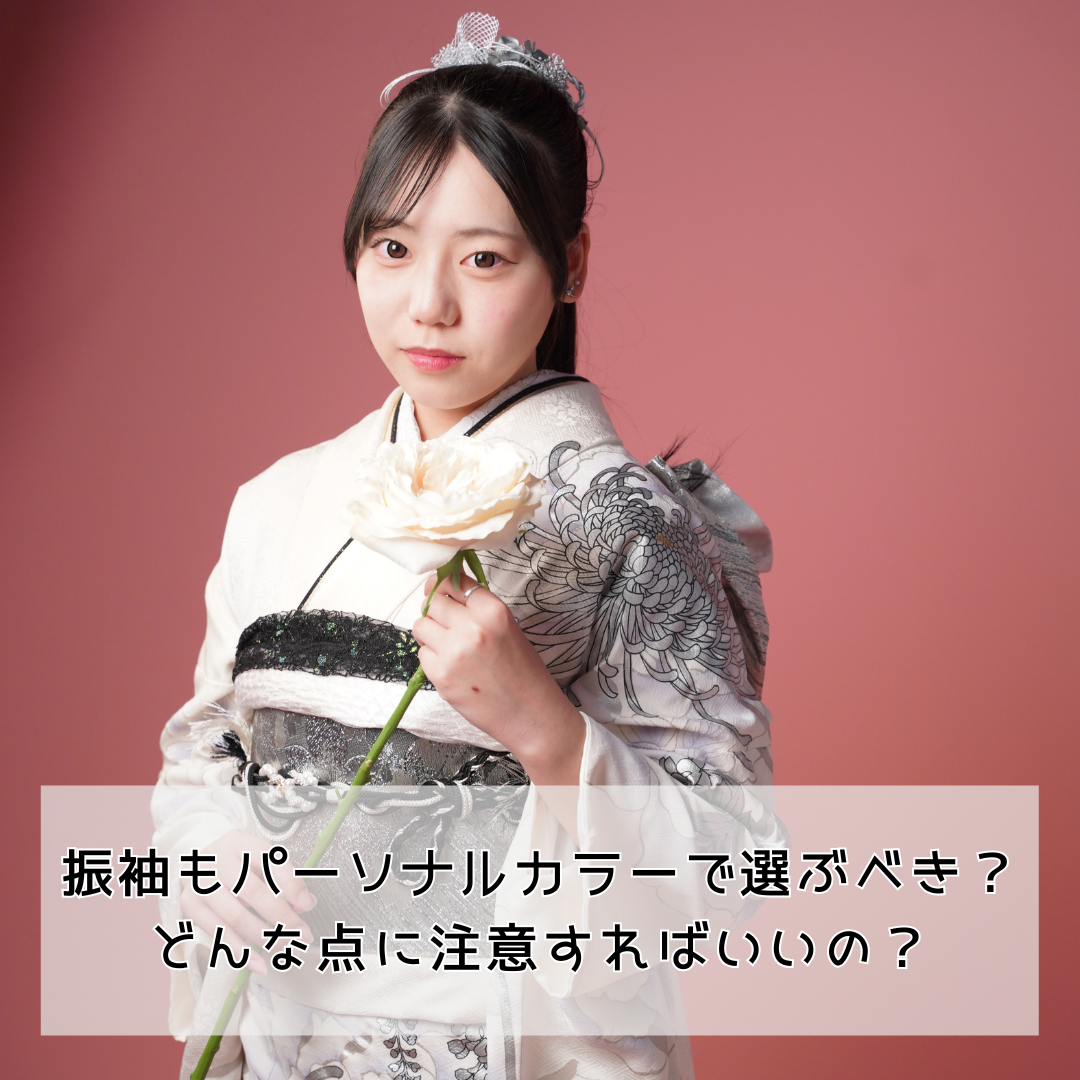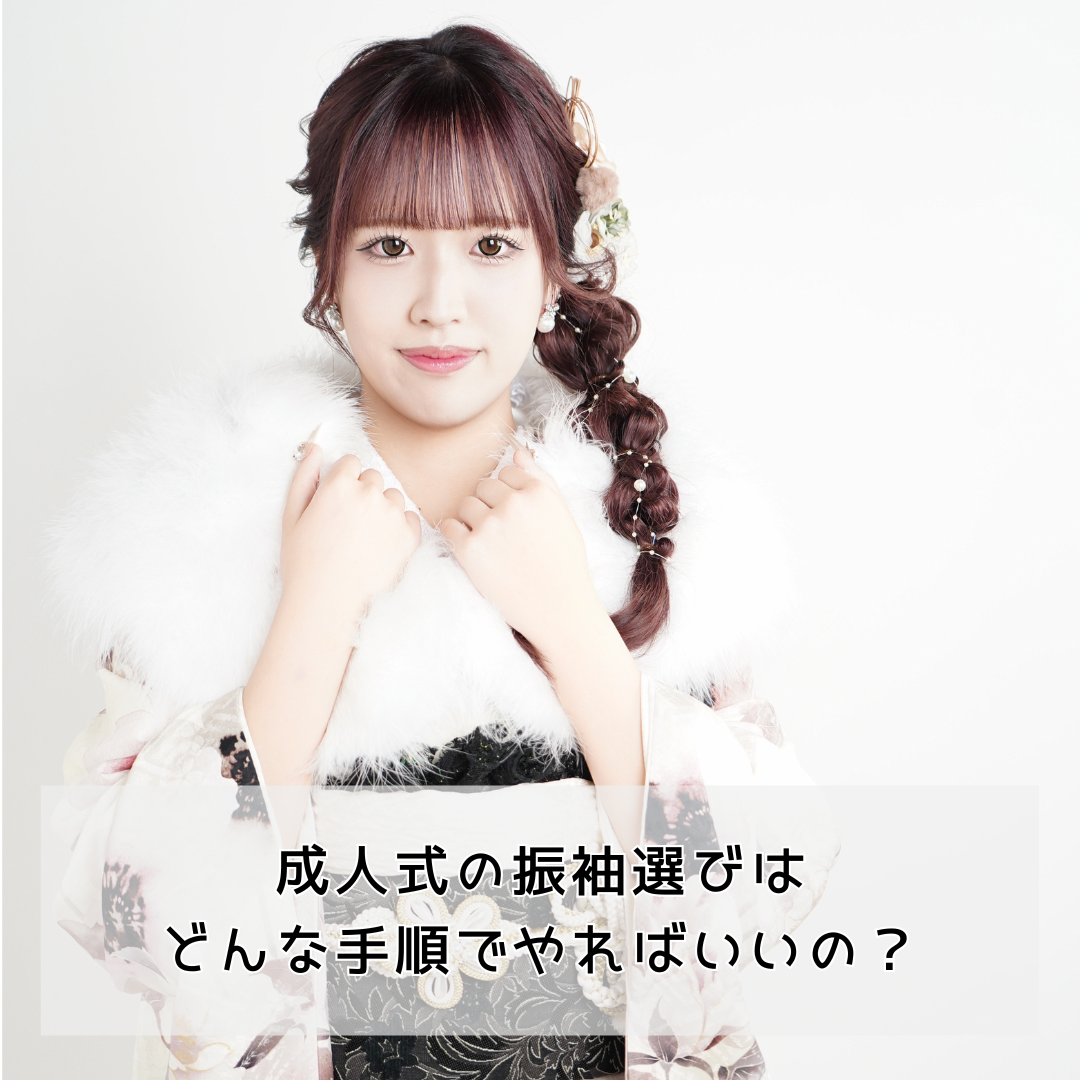振袖・袴まるわかり情報
- HOME
- 知って得する!振袖・袴まるわかり情報
- 成人式の歴史を知ろう!起源や由来をご紹介
成人式の歴史を知ろう!起源や由来をご紹介
2025/05/05
成人式は、若者が社会の一員としての自覚を持つための重要な儀式です。その起源を辿ると、古代の歴史にまで遡ります。
成人式のルーツは、中国の通過儀礼「冠礼(かんれい)」にあるとされています。
この儀式では、成人した男子に冠をかぶせることで、一人前として認められました。この風習が日本に伝わり、奈良時代以降、独自の発展を遂げました。

成人式の起源と歴史:その始まりを探る
奈良時代の成人儀礼「元服」と「裳着」
日本における成人儀礼の最初の形は、奈良時代の「元服(げんぷく)」と「裳着(もぎ)」です。元服は主に男子が対象で、11歳から16歳までの間に行われ、髪型を大人のものに結い直し、成人名を授けられる儀式でした。一方、裳着は女子の儀式で、裳と呼ばれる衣服を初めて身に着け、髪を結い上げるなどして成人を迎えました。

成人式の進化:江戸時代から近代へ
時代が進むにつれ、成人式の形も変化しました。
江戸時代には、成人の儀式は武家や公家、庶民それぞれで異なる形式で行われ、特に武家においては、社会的な地位を示す重要な儀式として重んじられました。
また、この時代には「振袖」の文化が発展し、未婚女性の正装として定着しました。振袖を着ることで、女性が成人を迎えたことを表現しました。
戦後の成人式:現代の形の成立
現代の成人式の形が確立されたのは、第二次世界大戦後のことです。1946年、埼玉県蕨町(現蕨市)で行われた「青年祭」がその発祥とされています。この祭りは、敗戦で落ち込んでいた若者たちを励ますために行われ、好評を博したことで全国に広がりました。そして1948年、成人の日が1月15日に制定され、「大人になったことを自覚し、自ら生き抜こうとする成人を祝い励ます」日となりました。

成人の日の制定と現代の成人式
成人の日は、1973年に1月の第2月曜日に変更され、現在に至ります。
この変更は、連休を増やすことで経済効果を狙った「ハッピーマンデー制度」の一環として行われました。
成人の日には、多くの自治体で成人式が開催され、振袖やスーツを着た新成人たちが集います。
振袖に込められた意味
成人式といえば、女性の振袖姿が印象的です。この振袖には、古来より「神を呼び起こし厄を払う」という意味が込められています。
特に、成人を迎える女性は厄年にあたることが多いため、振袖を着ることで厄払いを願う習慣が生まれました。
振袖の長い袖は、江戸時代から未婚女性の正装として定着し、現代でもその風習は続いています。

成人式の意義と未来への希望
成人式は、単なる年齢の到達を祝うだけではなく、社会の一員としての自覚を促す重要な節目です。
戦後の混乱期においても、次世代を担う若者たちへのエールとしての役割を果たしてきました。
現代においても、成人式は新成人が自らの未来を思い描く大切な機会であり、社会全体が若者を支える意義深い儀式です。
成人式の歴史を知ることで、この儀式が持つ深い意味を再確認できます。
新たな一歩を踏み出す若者たちを祝福し、彼らの未来がより良いものとなるよう、私たちもサポートしていきましょう。