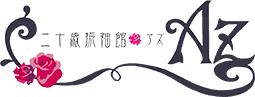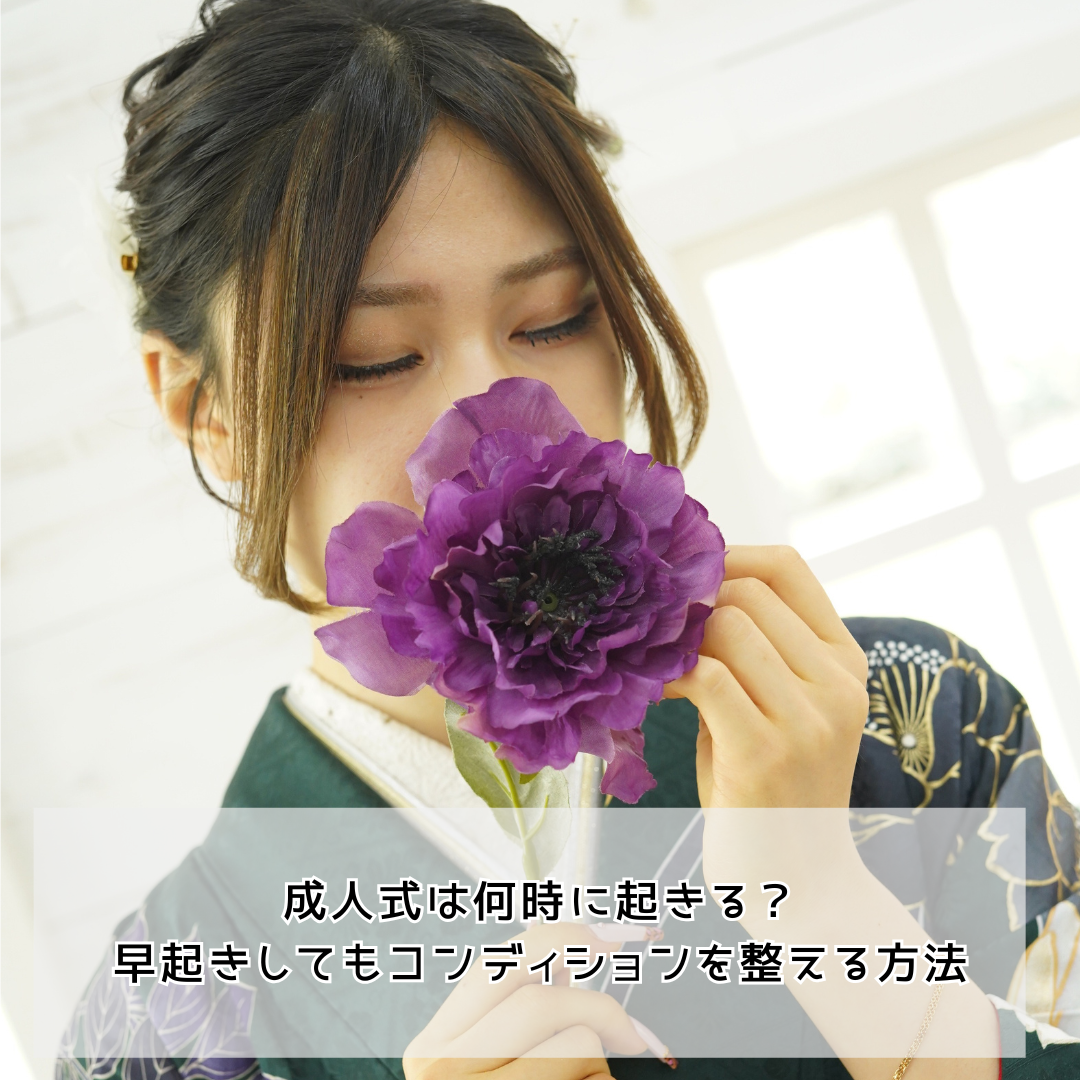振袖・袴まるわかり情報
- HOME
- 知って得する!振袖・袴まるわかり情報
- 成人は20歳?18歳?成人式は何歳の時に開催されるの?
2022年4月1日、日本の民法は約140年ぶりに改正され、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
この変更により、法的には18歳から「大人」としての権利と責任を持つこととなりましたが、社会的な側面ではまだ多くの議論が残されています。
特に注目されるのが、成人式の対象年齢です。法律上の変更があっても、成人式は従来通り20歳を対象に行う自治体が多いのが現状です。
このように、法律と社会慣習の間には微妙なズレがあり、多くの人々が戸惑いを感じています。
成人式の年齢、なぜ20歳が主流なのか
成人式を20歳で行う主な理由には、18歳が受験や就職活動などで多忙な時期であること、飲酒や喫煙が20歳以上に限定されていることなどがあります。これに加え、地域ごとの判断が大きく影響しており、自治体によっては「二十歳の集い」と名称を変更する動きも見られます。成人式の年齢については、法律変更によって必ずしも18歳にしなければならないという規定はないため、今後も各自治体が独自の判断で開催時期や名称を決定していくことでしょう。
成年年齢の引き下げとその影響
日本における成年年齢は、2022年4月1日から20歳から18歳に引き下げられました。この変更は、約140年間続いた成年年齢を改正するものであり、社会において大きな影響を与えました。成年年齢の引き下げにより、18歳から契約行為やクレジットカードの作成などが可能となり、法的に「大人」として認められることになります。しかし、この法改正が直接成人式の年齢に影響を与えるかどうかは、また別の問題となっています。
成人式の現状と自治体の対応
成人式は、多くの日本の市区町村で20歳を対象に行われてきました。成年年齢が18歳に引き下げられたにも関わらず、成人式の開催年齢は多くの自治体で20歳のままとされています。この理由としては、18歳が高校3年生であり、受験や就職活動で忙しい時期に成人式を開催することは難しいという現実的な問題があります。また、飲酒や喫煙の年齢制限が20歳以上であるため、成人式での飲酒などのリスクを避ける目的もあります。
自治体の判断に委ねられる成人式
成人式の開催年齢は、各自治体の判断に委ねられています。これにより、全国的に統一された年齢設定は存在せず、自治体ごとに異なるアプローチが取られています。一部の地域では、18歳を対象に成人式を開催する自治体もありますが、ほとんどの自治体は従来通り20歳を対象にしています。さらに、成人式の名称を「二十歳のつどい」などに変更する動きも見られます。
成人式の未来と社会的な役割
成人年齢が18歳に引き下げられたことで、今後の成人式のあり方についても議論が続いています。成人式は単なる式典ではなく、若者が大人としての自覚を持つための重要な社会的なイベントです。そのため、自治体や地域社会がどのようにこの式典を位置づけるかが問われています。
法律改正の背景と目的
成年年齢の引き下げは、若者の社会参加を促進し、早期からの自立を支援することを目的としています。これは、社会の変化に対応し、若者がより早くから社会の一員としての役割を果たすことを期待するものです。しかし、法律の改正と社会の慣習とのギャップが存在するため、成人式の年齢変更には慎重な検討が必要とされています。
成人式参加者へのアドバイス
成人式に参加予定の方は、自分が住む自治体のホームページや広報誌で詳細を確認しておくことが重要です。自治体によっては、成人式の年齢や開催時期が異なる可能性があるため、最新の情報を入手しておくことで安心して参加することができます。また、式典に参加することで、大人としての自覚を持ち、社会に貢献する意識を高める良い機会となるでしょう。
まとめ
成人年齢の引き下げは、日本社会における法的な「大人」の定義を大きく変えるものでした。しかし、成人式の年齢に関しては、法律とは別に社会的な慣習や実際の状況が影響を与えています。自治体によって異なる対応が取られているため、今後も各地域での成人式がどのように進化していくのか注目されます。成人式は若者が大人になる重要な節目であり、今後もその意義を見直しつつ、時代に合わせた形で維持されていくことが期待されます。